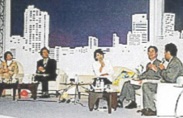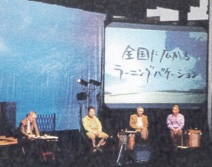地域活性事業とは、各地域における経済や文化を活発化し、「 地域住民の地域活動へ向けた意欲向上 」や「 持続可能な地域社会の創出 」など、活気のある街作りを進めていく取り組みです。
私は2003年から国土交通省、経済産業省主催の地域活性化事業に携わっていました。
私が携わっていたのは、地域住民の意識向上や、その成果を発表するシンポジウムの構成演出を担当し、主に「食」や「文化」 その地域の新しい価値観を掘り起こす為の「観光」に特化した取り組みが多かったです。
この頃、小泉純一郎首相が、日本の観光は重要な国家政策の課題 である!と提唱し「観光」を経済産業の柱として発展させようと力を入れていた時期でした。
その当時、新しい観光資源の掘り起こしとして、農業や漁業体験、と言ったいわゆるグリーンツーリズムの「体験型観光」や アニメや映画、ドラマ制作の映画関係者を誘致する「フィルムコミッション」を推進する取り組みなどがありました。また「クールジャパン戦略」以前に外国人観光客を呼ぶために、外国人ウケする新しい「グルメ」や「サブカルチャー」を紹介し、日本各地は観光誘致の取り組みが盛んに行われていました。
今では日本の観光地は、インバウンドの増加でオーバーツリズムだと社会問題になっていますが、これは この当時 日本に外国人観光客を誘致するにはどうすれば良いか……と言うことしか考えていなかった 当時の経済産業省の功罪だと思っています。
さて、行政シンポジウムって、基本的に啓発を目的とした討論内容で、その道の専門家や有識者のアドバイスを語るだけだから、演出なんて必要あるの?と思われがちですが、その通り主催者側で課題のテーマを決めて、ファシリテーターがそのテーマに沿った議論で進行するシンポジウムもあります。
しかし専門家同士が議論する内容だと専門用語が飛び交い一般的に話が分かりづらく、面白味もないシンポジウムになってしまいがちです。依頼案件のほとんどは、元リクルートの藤崎慎一 氏(現地域活性プランニング代表)からで、当時は堅苦しい行政イベントの既成概念を覆し、地域住民に分かりやすく訴求させるためにエンターテイメント的な面白い演出を藤崎氏プロデュースで様々な地域で手掛けさせてもらいました。
私が手掛けたのは、ファシリテーター任せではなく、1から構成の立案、台本の骨子やテーマに沿った進行の流れを構成する必要が有り、司会者やファシリテーターの進行台本は全て私が作成しなければなりませんでした。
地域の問題はそれぞれ千差万別で取り組み事例の取材は一筋縄では行かないので大変でしたが、地域活性のシロウトが切り込んだだけに行政イベントの既成概念を少しは変えられたのかも知れません。
当時 私が構成した演出は、専門家の言葉だけでは伝わりづらい内容を、発言のタイミングに合わせて、映像をインサートさせ、討論内容と映像をリンクさせる手法を行っていました。また、イベント内容は、90〜120分の限られた時間しかないので 参加する地域住民に「事業の目的」を分かりやすく明確に伝えなければならないので 役者を起用し、舞台で議論となるテーマに沿った寸劇を行ったり、取り組みの事例やインタビュー映像を用いて、見て聴いて分かりやすく伝えるように 「起・承・転・結」がある構成内容で各種シンポジウムを手がけていました。
ひとえに地域活性と言っても、その地域の特性に合致した取り組みを推進しないとならないので、各地域の取材に悪戦苦闘した記憶しかありませんが、 日本が「観光立国ジャパン」と躍起になっていた20年前、地域を元気にする「地域活性」という言葉も浸透していない頃、様々な地域の取り組みに立ち会え、取材に応じてくれた多くの関係者の方々には今では感謝の言葉しかありません。
この仕事に携わっていた2003年は官民をあげたインバウンド促進策が作られた年で、この政策が功を奏して、右肩上がりで観光客数は増加し、 訪日外国人客は年間3000万人を超え、コロナ禍が収束した24年は3687万人と過去最高の記録となっていると報道されています。
しかし 観光客が集中する地域では、いわゆる「オーバーツーリズム」が深刻化し、訪日外国人客の受け入れる環境整備は年々問題視されています。
地域活性事業には、功績と罪過 、良い面も悪い面もありますが 日本経済を潤すために 観光をテコに地方都市を活性化し、持続可能な「観光立国」を目指してほしいと思います。